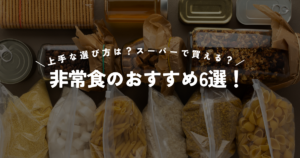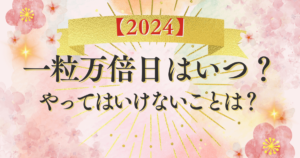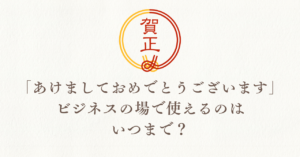近年、地震や台風などに加えて、豪雨や竜巻といった自然災害が増えています。いつ起こるか予測できない災害から身を守るためにも、万が一の災害に対する備えが必要です。
そんな「災害大国」とも呼ばれる日本には、年に一度、もしもの災害について考える「防災の日」があります。
今回は、「防災の日」が制定された理由や災害に備えておくべき防災グッズリストについて紹介します。
「防災の日」は防災意識を高める年に一度の記念日
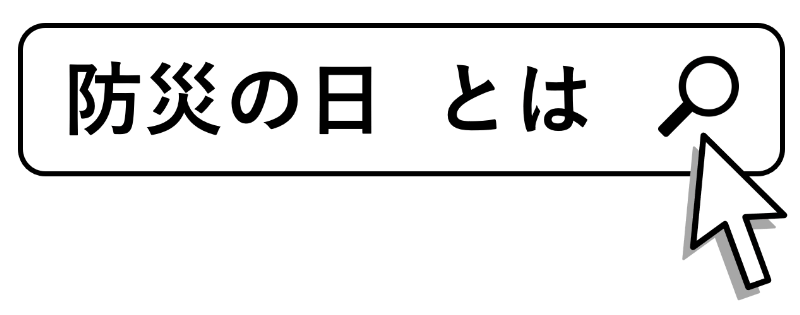
日本にはさまざまな記念日がありますが、「防災の日」もその内のひとつ。しかし、「防災の日」は国民の祝日ではないため、誰もが知る記念日といえるほどメジャーではありません。
「初めて聞いた」という方もいるかもしれませんね。「防災の日」は、防災の意識を高め、心がまえを準備する日として、1960年に制定されました。
いつどこで起こるか予測できない、地震・豪雨・竜巻・土砂崩れ・火山の噴火など、ありとあらゆる自然災害の防災について考える、年に一度の記念日です。
毎年「9月1日」が防災の日となった由来
「防災の日」は、毎年9月1日と決まっています。曜日は関係なく「9月1日」が防災の日にあたります。
なぜ、防災の日をこの日に制定しているのか。その由来は次の2つです。
- 1923年に発生した「関東大震災」の発生日
- 台風が発生する厄日「二百十日(にひゃくとおか)」にあたる
関東地方で大きな被害を出した「関東大震災」の発生日であることに加えて、暦上で台風が発生すると言われている「二百十日」にもあたる、9月1日。
「防災の日」を制定した日にちからも、これまで多大な被害を受けた自然災害を防止しよう、という想いを感じられますね。
防災の日を含む7日間は「防災週間」
9月1日の防災の日を含む7日間(8月30日~9月5日)は、防災について今一度考える期間「防災週間」として制定しており、防災週間・防災の日には、全国各地で防災について考えるイベントを開催しています。
自治体によっては、大地震体験や、災害時に活躍する特殊車両を展示するなど、防災について五感で知ることができる「防災フェスタ」を実施していることも。
また、避難訓練をしたり、防災についての学習を取り入れたりする小学校・幼稚園も多いようです。給食のメニューに、実際に災害を体感できる「防災食」を出すところもあるのだとか!
もしもの災害時に備えたい「防災グッズ」10選

繰り返しになりますが、災害はいつ・どこで起こるか、まったく予測ができません。東北出身の筆者も、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」で被災。
電気・水道・ガスといったライフラインがすべて止まっただけでなく、交通インフラも停止し、万が一の備えの大切さを身にしてみて体感しています。
災害は、忘れたころに突然やってくるもの。日ごろの備えが、いつかやってくる災害時に自分や家族の命を守ります。
今回は、筆者の被災経験をもとに、用意しておくと役立つ「防災グッズ」をピックアップしました。
飲料水
被災時、いちばん困ったのが水でした。非常用の水は、被災時に命をつなぐ重要な備えです。
生命を維持するためにも欠かせない飲料水は、家族の人数分用意しておきましょう。備蓄は、最低でも1人1L~1.5Lが目安です。
カクヤスでは、飲料水1本から宅配注文ができるので、気づいたときにストックをしておくといいですね。
非常食
飲料水と合わせて、非常時でもすぐに食べられる食料も必要です。断水したときのことも考えて、水なしで食べられるビスケットや、喉が渇きにくいゼリーなどがおすすめ。
非常用ではありませんが、チョコレートなどの甘いものもあると◎不安な心を、ほっと落ち着かせてくれます。
懐中電灯・ランタン
停電時にあかりを確保できるよう、懐中電灯やランタンは必ず用意しておきましょう。携帯用と部屋に置く用を、それぞれ買っておくと重宝します。
ラジオ
筆者が被災した際、停電の影響でテレビからの情報が得られない日が何日も続いたとき…。唯一、情報が入ってきたのが「ラジオ」でした。
今の時代、ラジオそのものを持っている人は少ないかもしれません。しかし、万が一の場合、スマートフォンの充電もできない日々が続きます。災害の備えとして、一家に一台ラジオがあると安心です。
乾電池
ラジオや懐中電灯、ランタンといった電気製品は、乾電池がなければ動きません。替えがきくよう、乾電池は多めにストックしておくことをおすすめします。
医薬品
万が一、けがをしたときに応急処置ができるよう、最低限の備えを用意しておきましょう。ばんそうこう・包帯・消毒液・ガーゼ・はさみのほか、常備薬などもストックしておくと良いですね。
持病をお持ちの方は、通院・処方できない場合も考えて、常に2~3週間分があると安心です。
衛生用品
水が止まると、入浴はもちろんシャワーさえ浴びることができません。
被災時に衛生を保つためにも、身体拭き・ウェットティッシュ・アルコールスプレー・マスクや、歯磨きシートなどの口腔ケアグッズも用意しておきましょう。女性であれば、ナプキンの買い置きも必須です。
もっとも需要なのは、「簡易トイレ」です。断水しているとトイレの水も流せなくなりますので、復旧するまで使える簡易トイレは多めに備えておきましょう。
ホイッスル
助けを呼ぶ際、「ホイッスル」があれば、大声を出さなくても気づいてもらえる可能性があります。
使い捨てカイロ
「東日本大震災」は、まだまだ冬の寒さが厳しい時期に起きた災害でした。停電で暖房器具が使えないときは、開封してすぐに温かくなる「使い捨てカイロ」があると手足の暖を取れます。
ガスコンロ
「ガスコンロ」は、ライフラインがすべて止まっても使える万能な調理器具です。調理だけでなく、お湯を沸かす手段としても活躍しました。
このほか、お子さんがいる方は、おむつやミルクの買い置きも必要となります。
今回紹介した防災グッズは、あくまで最低限そろえておきたいものの一部です。家族構成やライフスタイルに合わせて、必要なものを今一度考えてみてください。
防災グッズは「非常用持出袋」へ

災害時に過ごす場所は、自宅とは限りません。自宅にとどまるのが危険な場合は、安全な場所へ避難する必要があります。
万が一避難するとなったとき、いつでもすぐに持っていけるよう、防災グッズは「非常用持出袋」へ入れておきましょう。
「非常用持出袋」は市販の物でも良いですし、使い慣れたリュックやナップザックを使ってもOKです。
防災セットは3日分が限度

備えは多いに越したことはありませんが、持ち出すとなると量も問題。多すぎて運ぶのに手こずってしまえば、スムーズに避難できずかえって危険です。
とくに飲料・食料は重量があるため、入れすぎはNG。カンパンなどの比較的軽い非常食であっても、3日分を目安にしましょう。
防災グッズを安くそろえるには?
万が一の備えとして、防災グッズを備えておくことは重要ですが、気になるのはそのお値段。最低限のアイテムだけ買い揃えようとしても、出費は決して少なくありません。
ですがご安心を!防災グッズは、くふう次第でコストを抑えることも可能です。
100円ショップの商品を活用

生活用品をはじめ、なんでも揃う100円ショップ。実は、防災グッズの品ぞろえも充実しています!
筆者がダイソーで調べたところ、次の商品を販売していました。
100円商品ではないものの、水をためておく「給水タンク」や「ランタン」も、500円で販売していましたよ。
食料品はドラッグストアで

2022年の止まらない値上げラッシュにより、缶詰やレトルトなどの食料品も価格引き上げとなっています。
少しでもお安く買う手段としておすすめなのが「ドラッグストア」。食料品は、スーパーで買うよりも割安なことが多いです。
中でもマツモトキヨシやスギ薬局は、食料品に使える各種クーポンも配信していますので、割引も活用するとさらにコストを抑えられますよ。
年に一度、家族で「防災」の見直しを

いつもの日常を過ごしていると、いつ・どこで起きるかわからない災害について、じっくり考えることって、それほどないかもしれません。
今年の防災週間・防災の日も、まもなくやってきます。この機会に、防災について見直し、万が一の備えを準備してみませんか?