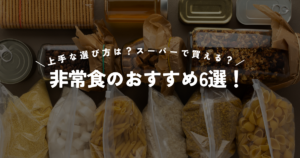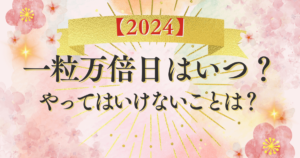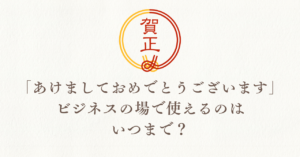1月といえば、年末の慌ただしい期間が過ぎ、年が明けた雰囲気を感じる時期。そして、「人日の節句」の1月7日はそういった少し落ち着いた頃であり、五節句の始まりでもあります。
ただ、人日の節句と聞いても何をするのかピンとくる方は少ないのではないでしょうか?
今回は、五節句のひとつでもある「1月7日 人日の節句」についての意味や習わしについて詳しくご紹介します。
記事の最後には、人日の節句がある1月にチェックしたいこと・避けたいことも紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね。
五節句のひとつ「人日の節句」とは?

まず、そもそも五節句って何?といった方に向けて、「五節句」についてを解説します。その後に「人日の節句」についても紹介していきますね。
人日の節句は「じんじつのせっく」と読みます。普段使わない言葉なので聞き慣れない方も多いでしょう。ぜひ本日から読み方を覚えてしまいましょう!
五節句の由来
五節句の”節句”とは季節の変わり目(節目)のことを指します。昔はこの時期に神様にお供えを行っていたので、節句ではなく節供と書く場合(読み方は同じ)もあります。
古代中国の陰陽道の考え方では1・3・5・7・9の奇数は陽であると考えられていました。しかし奇数が重なる日は陰の力が強い日と怖がられていたため、陰の力が強い日は身を清め神様にお供え物を行う日としました。
その陰の力が強い日が1年に5回あるということになります。
これらを五節句と呼んでおり、今回はその中の「1月7日 人日の節句」について紹介していきます。
なぜ「人日の節句」は1月1日ではなく1月7日なの?
先ほど、五節句は奇数が重なる陰の力が強い日とお伝えしましたが、1月7日の人日の節句以外は月と日が同じ(ゾロ目)ですが、人日の節句だけは異なります。
他の節句と併せて考えると1月1日になるものだと思いますが、1月1日は元日のため、別格として扱われています。また、中国の考え方ですが、元日から6日のそれぞれの日に獣畜を当てはめて占う習慣がありました。
- 1日=鶏
- 2日=狗(いぬ)
- 3日=羊
- 4日=猪
- 5日=牛
- 6日=馬
- 7日=人
1月7日は人が当てはめられていたため、人日の節句と言われるようになりました。
しかし、この考えが入ってくる以前にも日本には1月7日は七草粥を食べる習慣がありました。日本に元々あった七草粥を食べる習慣と中国からやってきた人日の節句の考えが合わさり、現在の人日の節句となっています。
「人日の節句」で行うこと

中国とも関連深い1月7日「人日の節句」ですが、行事として行うことは2つあります。ぜひこれらを行う意味を知って、人日の節句に実際に行ってみるのはいかがでしょうか。
春の七草を使った七草粥を食べる
旧年の厄や穢れ(けがれ)を払い、新しい一年の健康を願って、1月7日の朝に春の七草を使った七草粥を食べます。
七草粥を食べる風習が生まれたのは平安時代で、習慣として定着したのは江戸時代と言われています。江戸幕府は七草粥を食べることを公式行事と定めたことで、貴族達だけではなく庶民にも広がっていきました。
七草粥に入れる七草は地域によって多少異なりますが、今回は多くの地域で食べられている七草と意味を紹介します。
中には公園などに自生している場合もありますが、犬や猫の糞尿がかかっている可能性があります。見た目が似ている草の可能性もあるため収穫は避けましょう。
セリ:勝負事に「競り」勝つ
セリは鉄分が多く、血液量を増やす効果があります。全国の山野で自生しているため、全国の七草粥に使われています。若いセリは葉や茎が柔らかく、香りの良さが特徴です。
ナズナ:汚れを払う
ナズナは熱を下げ、利尿作用があります。ぺんぺん草とも呼ばれており、全国に自生しています。昔は冬の貴重な野菜として重宝されていました。
ゴギョウ:仏様をさす
ゴギョウは地域によってはハハコグサと呼ばれています。黄色い花を咲かせ、若い葉や茎であれば柔らかいので食べることが出来ます。
ハコベラ:子孫繁栄
ハコベラはタンパク質とミネラルが豊富に含まれています。ハコベ、コハコベと呼んでいる地域もあります。白い小さな花を咲かせ、おひたしや胡麻和えとしても食べられる場合も多いです。
ホトケノザ:仏様がゆっくりと座っている
ホトケノザ若菜のみ食用として使われます。
紫の花をつけるホトケノザは食用ではないため注意して下さい。
スズナ:神様を呼ぶための鈴
ジアスターゼが含まれており、消化を助けます。スズナは蕪(かぶ)の葉部分を指します。
スズシロ:清らかで汚れがない
スズシロは、ズズナにも含まれるジアスターゼが含まれています。大根の昔の呼び方です。
白馬の節会
1月7日は、白馬の節会(あおうまのせちえ)と呼ばれる節供行事が行われていました。
元々はこの行事が最も盛大に行われており、天皇陛下が紫宸殿(ししんでん=内裏の正殿のこと)で邪気を払うとされる白馬を観覧する節供行事でした。現在でも人日の節供に白馬を見ると、とても縁起がいいとされています。
京都の上賀茂神社、大阪の住吉大社では、人日の節句に白馬の神事が行われています。
1月にチェックしておきたいこと・できれば避けたいこと

1月7日の人日の節句に「今までなんとなく七草粥を食べていた…」という方も、本記事で意味などを理解することで、次回の人日の節句ではまた違った味わいになるのではないでしょうか。
「人日の節句」がある1月は、慌ただしかった年末を終え、年始シーズンとなります。ここからは、1月にチェックしておきたいことや、できれば避けたいことをご紹介します!
1月にチェックしておきたい「初売りセール」
1月のお正月といえば初売りセールがさまざまな店舗で行われます。毎年必ず開催するとは言い切れませんが、楽天市場やAmazonなどの大手ECサイトでは大幅な値下げセールが実施されています。
様々な商品が値下げ対象となりますが、特に牛肉やお米などの食品関連がやすくなりやすい傾向があります。来年も絶対に行われるとは言い切れませんが、年末年始は必ずチェックしましょう。
1月にチェックしておきたい「福袋」
お正月といえば「福袋」を毎年購入しているという方も少なくないのではないでしょうか。最近は中身もすべて見れる福袋も多く販売されており、中に入っている実際の価格よりもかなりお得な値段で販売されています。
新型コロナウイルスの影響で、オンラインのみの販売であったり、12月下旬から随時販売するなど今までの福袋の販売方法とは変化しています。お得な福袋をゲットするには10月くらいからよくチェックしておきましょう。
1月にできれば避けたい「家電製品の購入」
初売りセールや福袋の販売で、ついつい家電製品の購入をしてしまいがちですが、実は1月に家電家電を買うよりも2月のほうがよりお得な場合があります。
2月は1年で最も短いため、消費が一番落ち込む時期でもありますが、同時に決算時期も迫っているため、家電量販店はより多くの在庫を売りたいと考えます。
そのため、値引き交渉にも柔軟に応じてもらうことができるので、1月よりも2月のほうがお得です。
引っ越し
新年度や新生活を迎える前に、引っ越しをされる方も多いでしょう。しかし、よほどの事情がない限り1月に引っ越しをおこなうのはおすすめしません。
年末年始で引っ越し料金も上乗せされている上に、新年度を迎える繁忙期のためスケジュール的にもかなり融通がききません。
新年度までの1月~3月での引っ越しは避けて、余裕を持った11月頃などに行うようにしましょう。

1月は一年の始まり、人日の節句は五節句の始まり

今回は「人日の節句」の意味や、1月にチェックしたいことやできれば避けたいことなどをまとめて紹介しました。
五節句の中でもあまり意識されていない人日の節句ですが、七草粥を食べている家庭は多いのではないでしょうか。ぜひ次回の人日の節句には、春の七草それぞれの効能などを意識しながら食べてみてくださいね。
1月は一年の始まりであり、人日の節句は五節句の始まりです。人日の節句を祝い、いい年を迎えましょう。