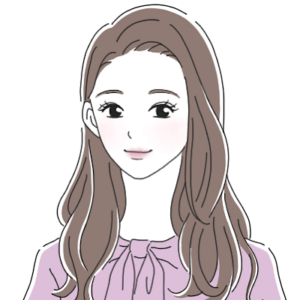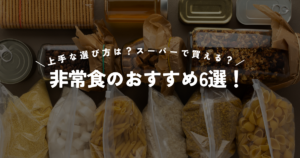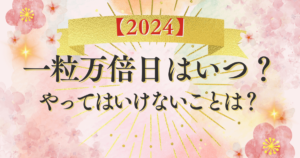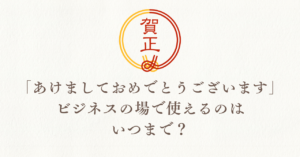「家計簿を始めたいけど何からしたらいいかわからない」「家計簿が続いた経験がない」など、お困りの方も少なくありません。
家計簿で1番大切なことは、家計簿をつける目標や目的を明確に決めることです。目標がなければ、家計簿を続けるのは難しいでしょう。
そこで、この記事では「家計簿の目標・目的の例」や「家計簿を始める前に決めること」、「家計簿の付け方」などを紹介します。
本記事を参考にしながら、ぜひ家計簿を作ってみてくださいね。
家計簿を始める前に決める3つのこと
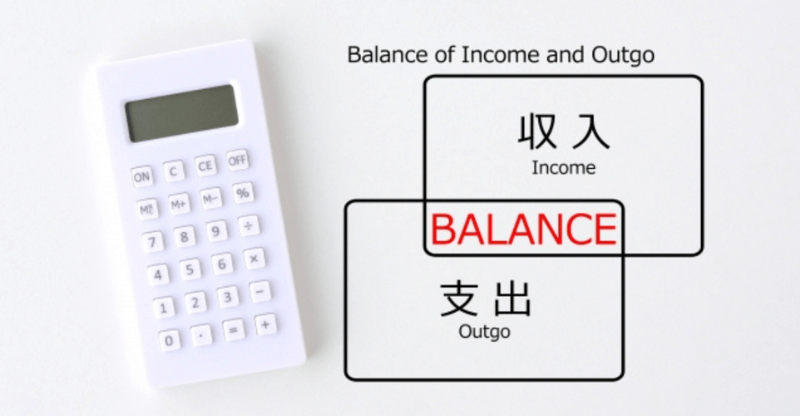
家計簿をつけ始める前に、まずは下記の3つを決めていきましょう。
- 家計簿をつける目標・目的を決める
- 家計簿の管理方法を決める
- 家計簿に記入する項目を決める
この3つを決めないと、まとまりのない家計簿になってしまうので最初に決めていきます。
その1:家計簿をつける目標や目的を決める
目標や目的がないまま家計簿をつけ始めても、ふとしたときに「家計簿は必要?」となってしまい、長く続きません。
そのようにならないためにも、何のために家計簿をつけるのかをはっきり決めておきましょう。
家計簿をつける目標や目的は何でも構いません。まずは、自分がやる気の出る目標・目的を決めましょう。
家計簿の目標・目的の例:
- 貯金(結婚、旅行、教育資金、マイホーム、老後資金など)
- 支出の管理(どのくらい使っているのか明確に知りたい)
- 無駄遣いを減らしたい
- 資産形成、資産運用をしたい など
その2:家計簿の管理方法を決める
目標や目的を決めたら、家計簿の管理方法を決めていきます。
代表的な家計簿の管理方法は下記の4つです。
- ノートに手書きで記入する
- 家計簿ノートを購入して記入する
- 家計簿アプリを利用する
- Excelで表を作って管理する
管理方法は続けやすいやり方を選びましょう。
手書きのほうが管理しやすく、やる気の出る方は、ノートや家計簿ノートがおすすめです。一方、キャッシュレス派の方は家計簿アプリと銀行・クレジットカードをつなげて自動入力を活用するほうが楽かもしれません。
それぞれのライフスタイルや性格に合った管理方法を選びましょう。
その3:家計簿の構成・記入する項目を決める
最後に、家計簿の構成や記入する項目を決めていきます。
家計簿の構成は主に下記の4つです。
- 目標貯金額(貯金が目的の場合)
- 固定費
- 変動費
- 収支の合計
目標・目的を記入する箇所を作る
ノートの余白部分や上部など、どこでもいいので最初に目標と経過を記入できる箇所を作成しましょう。
家計簿をつける目的を見失わないための大切な準備です。家計簿をつける目的が貯金の場合は、目標貯金額と毎月貯金する貯金額を決めて記入しましょう。
例:
| 目標金額 | 今月の目標貯金額 | 実際に貯金できた額 | 現在の合計貯金額 |
| 100万 | 3万 | 2万 | 2万 |
固定費の項目を決める
固定費は毎月あまり変動しないお金のことです。
- 家賃
- 光熱費
- 通信費
- 各種ローン
- 教育費
- 保険
- サブスク
- 積立投資 など
ここの段階で、毎月の必要な最低金額を見える化できます。
もし、削減できる箇所があれば積極的に見直しをしていきましょう。
変動費の項目を決める
変動費の項目を決めていきます。
細かく設定しすぎると、面倒に感じて続かなくなる可能性もあります。そのため、大まかな設定で問題ありません。
- 食費
- 日用品
- 外食
- 医療費
- 特別費
- 娯楽費
- お小遣い
- 交通費 など
収支の合計
最後に、収支の合計を記入する箇所を作ります。
収入に対して、支出がどのくらいあったのか把握できる場所になります。もし収入より支出が多かった場合は、どこを使いすぎたのか見直すことが大切です。
収支の合計は、最初のほうで作っても問題ありません。管理しやすい場所に作成しましょう。
家計簿のつけ方簡単4ステップ

目標や記入する項目を決めたら、実際に家計簿をつけていきましょう。
ステップ1:収入から固定費・貯金を差し引く
まず、収入から固定費と貯金額を差し引きましょう。
固定費はほぼ変動しないので先に差し引いておきます。そして、貯金が目的の場合は先取り貯金を徹底しましょう。
残ったお金を貯金する方法もありますが、最終的に利用してしまい貯金するお金が残らない可能性が高いです。
そのため、確実に貯金をしたいなら先取り貯金がおすすめです。
ステップ2:変動費の予算を決める
収入から固定費と貯金を差し引き、残ったお金で生活していきます。
変動費の項目は「変動費の項目を決める」のところで決めているはずなので、決めた項目ごとに予算を決めていきましょう。
最初は残ったお金を越えなければ、おおまかで問題ありません。家計簿を続けながら予算を調整していきましょう。
予算を決めたら、封筒や仕分けしやすいケースなどに分けていれていきます。買い物やお出かけの際はそのお金を持って予算内で使っていきましょう。
ステップ3:支出を記入する
お金を使ったら、家計簿に記入します。
レシートを持って帰ってきてもいいですし、レシートの写真を撮ってレシートを溜めないようにする方法でも問題ありません。
また、家計簿アプリやExcelを利用する方はその場で記入したり、クレジットカードの反映を待って項目を仕分けしたりしましょう。
ステップ4:収支を把握する
最後に、収入から支出を引いて今月が赤字か黒字かを把握しましょう。赤字の場合は、見直して改善していくことが大切です。
また、家計簿を開始する日と締める日はいつでも問題ありません。「毎月1日〜月末まで」や「給料日を起点にする」など、家庭に合った期間で管理していきましょう。
家計簿を続けるコツ!

最初はやる気が出ているので続けられますが、時間の経過とともに家計簿のつけ忘れが出てくる方がいらっしゃいます。
一度つけ忘れると中途半端になり、つけたくなくなるので、間隔をあけてしまわないように注意しましょう。
家計簿を続けるコツを3つ紹介します。
コツ1:段階的な目標を設定する
家計簿は目標や目的なしに続けるのは難しいです。そして、大きな目標だけしか決めていない場合、達成感を味わうタイミングがなかなかありません。
そのため、大きな目標と小さな目標の2つに分けましょう。
例えば、大きな目標は【1年で100万円】を貯金すること。そして、小さな目標は【毎月8万4,000円】貯金することです。
このように、目標を大小の2つに分ければ達成感が毎月味わえ、続けやすくなるのでおすすめです。
コツ2:家計簿はシンプルにする
初めて家計簿をつけるときは、項目を細かく分けがちになります。しかし、細かすぎる項目設定は見直しにくい家計簿になる可能性が高いです。
そのため、できるだけ必要最低限の項目に分けて管理しましょう。もし、細かいほうが管理しやすい方は、そのままで問題ありません。
自分が見直しやすい家計簿で管理していきましょう。
コツ3:家計簿の時間を作る
家計簿に記入する時間、見直す時間を作るようにしましょう。
支出はできるだけ毎日記入したほうが、支出を把握しやすく無駄遣いの防止になります。しかし、仕事や家事で忙しい方は、1週間に1回記入する時間を作ってください。
また、家計簿の締め日は家計簿の見直しの日と決めておきます。その月の収支を把握し、次の月の予算や目標を決める必要があるからです。
忙しくても時間を作って定期的に見直しましょう。
大切なのは実践!今日から家計簿をスタートしよう!

家計簿を始める前に大切なことや、家計簿のつけ方を紹介してきましたが、重要なのは実践することです。
実際に、家計簿を使ってみないと自分に合っている方法はわかりません。私も3〜4回家計簿の管理方法や項目の種類を変えています。
最初から完璧な家計簿を目指さず、まずは行動していきましょう。