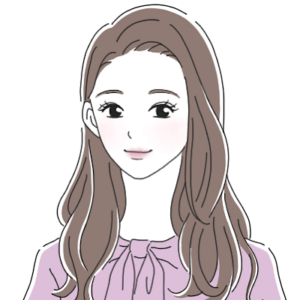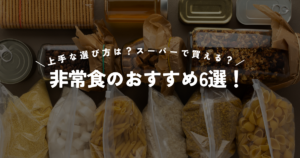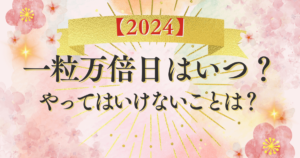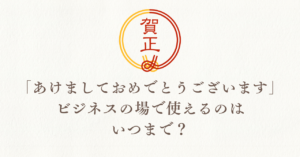出産ははじめてのことで、何をしたらいいかわからない方が多いでしょう。
妊娠後期は出産準備や内祝いのお返し決めなどやることが多くなるので、妊娠中期頃までに必要な手続きを把握しておくと、焦らずスムーズに進められます。
この記事では、「産前産後に必要な届出や手続きの種類」「医療費が高額になったときの対処法」など紹介しているので、出産を控えている方には必見の内容になっています。
ぜひ、旦那さんと一緒にみてください。

【全員OK】出産前に必要な届出・手続き

誰でも申請できる出産前に必要な届出や手続きについて紹介します。
今回紹介するのは下記の3つです。
- 妊娠届・妊婦健診の助成
- 出産育児一時金
- 限度額適用認定証
しかし、必ず出産前に申請しなければいけないのは1つ目の「妊娠届と妊婦健診の助成」のみです。
ほかの2つは出産前にしておいたほうが自己負担額が軽減されるため、出産前に必要な手続きとして紹介します。
(1)妊娠届を提出・妊婦健診の助成
まず、心拍が確認でき、病院から「次回までに母子手帳をもらってきてください。」と言われたら、妊娠届出書を住んでいる自治体へ提出しましょう。
妊娠届出書を提出後、母子手帳をもらうときに「妊婦健診の助成」も一緒に受け取れます。
妊婦健診の助成とは、妊婦健診代を一部負担してくれる制度です。約14回分(自治体により変動する)の回数券のような冊子がもらえます。
14回以上の検診が必要になったときは、自己負担です。
(2)出産育児一時金の申請
出産育児一時金とは、加入している健康保険から子ども1人につき「42万円」もらえる制度です。出産するときは、入院・分娩に高額な医療費がかかってきます。その負担を少しでも軽減できるようにつくられた制度です。
出産前に申請をした場合は、もらえる42万を超えた額だけを退院時に支払えば問題ありません。
しかし、出産前にこの手続きをする場合、「直接支払制度」が利用できるか病院に確認する必要があります。利用できない場合は、出産後にしか手続きできません。
出産後に申請をする場合は、一度全額自己負担で支払い、後日42万円が戻ってきます。手続きは、産院・病院でおこないましょう。
(3)限度額適用認定証の申請
限度額適用認定証とは、医療費が高額になった場合でも自己負担限度額までの支払いで済むようになる制度です。
自己負担限度額は収入によって左右されるので「全国健康保険協会」を参考にしてください。
| 申請方法 | |
| 国民健康保険の場合 | 住んでいる役所の国民健康保険窓口で申請 |
| 健康保険の場合 | 保険証に記載されている健康保険組合へ申請 |
帝王切開や吸引分娩などの医療行為が対象なので、申請しておいたほうが後日のお会計時に安心できます。
【全員OK】出産後に必要な届出・手続き

出産後で体がボロボロのなか、出産後に何の手続きをしたらいいか調べるのは大変です。事前に把握しておくことで、旦那さんにも共有でき、奥さんの負担を軽減できます。
出産後に必要な手続きは下記の通りです。
- 出生届
- 育児手当の申請
- 子どもの健康保険への加入
- 乳幼児・子どもの医療費助成
(1)出生届
出産してから14日以内に住んでいる自治体の役所へ出生届を提出しましょう。
出生届は、子どもを戸籍に登録する手続きです。
(2)児童手当の申請
出生届と一緒に、児童手当の申請もおこないましょう。申請が遅れると遅れた分の手当はもらえないので、注意してください。
児童手当とは、3歳までの子どもを育てている家庭に1人につき「1万5,000円」が支給される制度です。支給額は年収によって変動するので、事前に確認しておきましょう。
また、2022年10月からは年収が1,200万円を超える世帯には児童手当の支給が廃止となります。
(3)健康保険の加入
子どもを両親どちらかの健康保険の扶養へ加入させます。
会社員の場合は、会社で手続きをしてもらう必要があります。必要書類をあらかじめ確認しておくと、出産後スムーズに手続きができるでしょう。
国民健康保険の場合は、出生届と児童手当の申請と一緒に役所で手続きができます。
(4)乳幼児・子どもの医療費助成
子どもの健康保険証が届いたら、医療費助成の手続きをしましょう。
乳幼児・子どもの医療費助成とは、子どもが病院で診てもらったときにかかる医療費を全額または一部を助成してくれる制度です。
手続きは、住んでいる自治体の役所になります。手続きが完了後「乳幼児医療証」が届くので、病院に行くときは健康保険証と一緒に持っていきましょう。
【会社員限定】出産前後に必要な届出・手続き
出産に関して、会社員の方限定の手当があります。
- 産前産後休業(産休)の申請
- 出産手当金の申請
- 育児休業給付(育休)の申請
すべて会社へ申請するものになるので、事前に提出する書類など確認しておきましょう。
(1)産前産後休業の申請
産前産後休業(以下:産休)は、出産前後に会社の休みを取得する制度です。
| 産休期間 | |
| 産前 | 出産予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合は14週間前) |
| 産後 | 出産の翌日から原則8週間 |
産前の産休は申請した場合のみ取得できます。産前の産休を取得したいなら早めに上司や会社へ相談するようにしましょう。
産後の産休は、取得義務があるので申請手続きは必要ありません。しかし、会社によっては提出する書類や引き継ぎなどがあるのでこちらも事前に相談しておきましょう。
(2)出産手当金の申請
出産手当金は産休中の手当金です。しかし、産休中毎月支給されるのではなく、出産後数ヵ月後にまとめて振り込まれます。
手続き方法はこちらです。
- 産休前に会社で書類をもらう
- 記入した申請書を入院時に病院へ提出
- 出産後、病院に必要事項を記入してもらい受け取る
- 出産後、会社に記入済みの申請書を提出
支給額は加入の健康保険から1日あたり「日給の約3分の2」です。振り込みに時間がかかるので、支払いや引き落としには気をつけましょう。
(3)育児休業給付金の申請
育児休業給付金(以下:育休)は、取得したい方のみ申請します。
育休は子どもが満1歳になるまで取得できます。保育所に入れないときは2歳を迎える前日まで取得可能。育休手続きは、会社から書類をもらい、出産後に提出すれば問題ありません。
申請後、数日で給付金が振り込まれ、2ヵ月に1回振り込みがされます。支給額は1日あたり「日給の67%・半年後50%」です。
医療費が高額になったときどうする?

妊娠・出産は何が起こるかわかりません。想像以上に医療費が高額になることもあります。そのときのために、利用できる制度を確認していきましょう。
(1)1ヵ月の医療費が高額になったら高額療養費
先ほど産前に必要な手続きでも紹介した「限度額適用認定証」と同じ制度です。産前に手続きができなかった人は、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費を申請しましょう。
事後2年以内であれば申請可能で、申請から約1〜3ヵ月後に振り込まれます。
(2)年間の医療費が高額になったら医療費控除
医療費控除は妊婦さんだけでなく、家族全員で年間10万円越えの医療費がかかった場合、確定申告をすれば税金が戻ってくる制度です。
申請先は税務署です。確定申告まで、領収書と医療費のお知らせは大切に保管しましょう。確定申告の時期は翌年の3月15日までです。
損をしないためにも出産前後に必要な手続きを把握しよう!

出産前より、出産後にする手続きのほうが多くなっています。産後に奥さんが手続きに行くのは身体的に負担が大きいです。
そのため、旦那さんと届出や手続きの流れを一緒に把握して、旦那さんができるところはしてもらうようにしましょう。