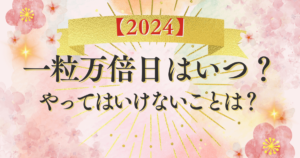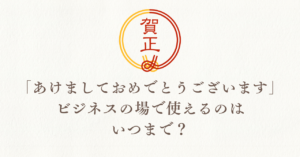五節句の中で「上巳の節句」といわれても、あまりピンとこないな…といった方も少なくないでしょう。
上巳の節句とされる3月3日は「桃の節句」や「ひな祭り」といった女の子の節句として有名です。反対に、5月5日の五節句「端午の節句」は、男の子の節句と呼ばれます。
現在も色濃く残っている上巳の節句ですが、今回の記事ではどんな意味や習わしがあるのかを詳しく解説します。また、記事の最後には3月中にやっておきたいこと・避けるべきことも紹介しているので参考にしてくださいね。
五節句のひとつ「上巳の節句」って何?

まず、「五節句」を聞き慣れない方のために「五節句」の由来を解説します。その意味などを理解してから「上巳の節句」についても紹介していきますね。
上巳の節句は「じょうしのせっく」と読みます。普段使わない言葉なので読み方を初めて知った方もいらっしゃるかもしれませんね。
五節句の由来
五節句とは季節の変わり目をさしており、昔はこの時期に神様にお供えを行っていました。日付に関しては古代中国の陰陽道の考え方が使われています。
陰陽道では1・3・5・7・9の奇数は陽であると考えられており、逆に奇数が重なる日は陰の力が強い日と怖がられていました。
その中でも特に陰の力が強い日は年に5回あります。これらを併せて五節句と呼んでおり、今回紹介する「上巳の節句(3月3日)」もその中の1つです。
3月3日がなぜ「上巳の節句」と呼ばれるのか
現在は上巳の節句よりも、「桃の節句」や「ひな祭り」として認識されている場合が多いでしょう。
上巳の節句は元々中国の習慣であり、この日に水辺で身を清めていたそうです。日本に入ってきたのは平安時代で、草や木、藁などで作った人形に自分に降りかかる災厄を移して、海や川に流すことでお祓いを行う「流し雛(ながしびな)」を行っていました。
このような歴史から、上巳の節句には雛人形を飾り、娘の厄を払い美しく成長して幸せな人生を送ってほしいという親の願いが込められています。江戸時代には五節句の一つに加えられ、5月5日が男の子の節句に対して、桃の花や雛人形を飾る事から女の子の節句として定着しました。

「上巳の節句」の行事2つ

女の子の節句として、現在も受け継がれている3月3日の「上巳の節句」ですが、主な行事は2つあります。ぜひ行事の意味を知って、上巳の節句がきたら行ってみるのはいかがでしょうか。
節句にちなんだ行事食を食べる
上巳の節句には行事食というものが主に6つあります。それぞれには意味があるのでそれぞれ確認していきましょう。
- ひし餅
- ひなあられ
- 白酒
- 桃花酒
- はまぐりの潮汁
- ちらし寿司
ひし餅
緑・白・ピンクの3色のお餅を重ねており、学校の給食などでは3色ゼリーとして提供される場合もあります。蓮の緑⇒魔除け、菱の実の白⇒清浄、クチナシの赤⇒疫病除け、といった意味があり、健康な成長を願う食べ物です。
ひなあられ
コロコロとした小さなあられです。現在はあまり区別は無いようですが、関西と関東で形が異なります。関西⇒餅を干して揚げるあられ、関東⇒米粒を炙ったあられ、などがあります。
白酒
白酒を甘酒と勘違いしている方がいますが、全く別物です。甘酒はアルコールが含まれていないため、子どもでも飲むことが出来ますが、白酒にはもち米・みりん・米麹・焼酎などを混ぜ合わせ一ヶ月程熟成、すりつぶしたもの。
白くとろっとしている部分は甘酒と似ていますが、アルコール度数は10%前後であり、分類としてはリキュールになります。アルコールが含まれているしっかりとしたお酒のため、当然ながら子どもは飲めません。
桃花酒
お酒に桃の花びらを浮かべたり、漬け込んだりした桃花酒を楽しみます。ももとせ(百歳)を願います。
はまぐりの潮汁
はまぐりを潮汁(うしおじる)としていただきます。はまぐりの貝はすでに対になっている貝殻以外にピッタリと合うものは存在しません。そのため相性のいい相手を見つけ、いつまでも仲睦まじく過ごせるようにと願いが込められています。
ちらし寿司
ちらし寿司には多くの具材が混ぜ込まれています。エビ⇒長寿祈願、れんこん⇒見通しのいい人生、豆⇒健康勤勉、といったように、これらの山海の縁起のいい食材を彩りよく楽しみます。
雛人形を飾る
上巳の節句といえば雛人形です。元々、女の子の災厄を人形に肩代わりしてもらう習慣からきています。
最上段にはお内裏様とおひな様を飾り、この2人以外に3人官女、五人囃子、随身、仕丁の15人を「きまりもの」と呼んでおり、標準的な一揃いとされています。
ただ、全てを飾ることが難しい家庭では、最上段のお内裏様とお雛様だけのパターン、それに三人官女を加えたセットを飾る場合が多いです。
雛人形を早く片付けないと嫁に行き遅れる
「雛人形を早く片付けないと嫁に行き遅れる」と聞いたことはありませんか?これには諸説ありますが、娘を嫁に出すことが親の義務と言われていた時代では、娘を嫁に出すことを「片付ける」と言っていました。
そのため、雛人形をいつまでも片付けないと、娘がいつまでも片付かないということです。また、雛人形は女の子の災厄を引き受けてもらいますが、ずっと出しっぱなしでそばに置いておくと、再び汚れが戻ってくると考える方もいます。
3月中にやっておきたいこと・避けるべきこと

3月3日の上巳の節句について意味や由来などを理解すると、お祝い事をする際さらに気持ちが深まるものではないでしょうか。
「上巳の節句」が訪れると同時に春の新生活シーズンがやってきますね。4月からは新しい環境での生活がスタートしたり、物の買い替えなどがしたくなる時期。ここで最後に、3月中にやっておくといいことやできれば避けたいことをご紹介します。
◎車の売買
まずは車の売買です。車を売ろうか買おうか検討中の方は、3月中がおすすめです。ただし、ここでいう「車」とは新車ではなく中古車のこと。
3月は新生活に向けて車を手放す(売る)人と購入する人で活発になります。3月に購入してくれる人が増えるため、値引き交渉などにも柔軟に対応してくれる可能性が高いです。
また、1月から3月は車の需要が高まる事がわかっているため、1台でも多くの在庫を用意しようと買い取りにも積極的な傾向があります。そのため、買い取り査定金額も普段よりもアップする場合が多いので、売りたいと考えている方はこのタイミングで査定に出しましょう。
×引越し
引越しは繁忙期になると料金が上がるシステムです。可能であれば2~3月の引越しは避けたほうが良いでしょう。
新生活や新学期が始まる3月はまさに繁忙期。3月中でも後半の土日は最も人気のため、料金が高くなる上になかなか予約も取れません。
そのため、新生活や新学期にともなって引越しを検討しているのであればできるだけ早めに済ませておくか、荷物が少ないのであればレンタカーなどを借りて自力で行うことを検討してみましょう。

「上巳の節句」で幸せを願い、ひな祭りなどの行事を楽しもう

今回は上巳の節句の意味や習わし、3月中にやっておくといいことやできれば避けたいことについて紹介しました。
3月3日は桃の節句やひな祭りのイメージがある人は多くても、上巳の節句という呼び方はあまり聞き馴染みがなかったかもしれません。
食べるものや雛人形にも諸説ありますが、次の上巳の節句の際はそれらの意味などを思い浮かべながら行事を楽しんでみてはいかがでしょうか?